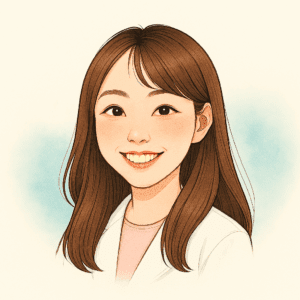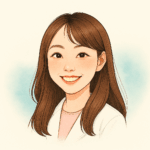
こんにちは!美腸通信を運営している皮膚科医ママのあーりんです🌸
今回はニキビのガイドラインの話をします!
まずみなさん、「ガイドライン」って聞いたことありますか?
医療の世界でいう「ガイドライン」とは、病気の診断や治療をしていくときに「標準的な方針」をまとめたものなんです。つまり、「この病気には、今の医学的な根拠に基づいて、まずはこの治療をおすすめしますよ〜」という、いわば“道しるべ”みたいな存在🍀
皮膚科領域でもニキビ(尋常性ざ瘡)やアトピーなど、各疾患ごとにガイドラインがあって、多くの専門家が最新の研究データを集めて検討し、安全で効果的な治療法を整理してくれています。
さて、ニキビはとても患者さんが多い病気なんですが、日本では保険がきかなくて自費診療になってしまう治療も、海外では強く推奨されていることがあるんです。代表的なのが「イソトレチノイン」という飲み薬ですね!
ガイドラインは日米で共通点もあれば違いもあって、ちょっとややこしいところも…。ということで日米のガイドラインを比べて整理してみることにしました✨
今回は、日本皮膚科学会による「尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン2023」(以下、日本ガイドライン)と米国皮膚科学会 による「Guidelines of care for the management of acne vulgaris」(2024年版。以下、米国ガイドライン)を比較しました。
日本での標準治療についてはこちら👇
- 日米のガイドラインで共通している基本方針
- 日米で“違い”が出る治療法
- 日本では保険がきかないけれど、海外では推奨されている治療の実情
推奨度について
まず、日本と米国で“推奨度の付け方”がどう違うのかを解説します🍀
🇯🇵 日本ガイドラインの推奨度の仕組み
日本皮膚科学会のガイドラインでは、以下の6段階評価が採用されています。
- A:行うよう強く推奨する
- A+:行うよう推奨する(A に相当する有効性のエビデンスがあるが,副作用などを考慮すると推奨度が劣る).
- B:行うよう推奨する
- C1:選択肢の一つとして推奨する
- C2:十分な根拠がないので(現時点では)推奨しない
- D:行わないよう推奨する
🇺🇸 米国ガイドラインの推奨度の仕組み
アメリカ皮膚科学会では、推奨の強さとエビデンス確実性の2軸で整理されます。
- Strong:強く推奨
- Conditional:条件付き推奨(患者背景や価値観によって選択)
- Strong/Conditional against:行わないことを推奨
- No recommendation(推奨を作れない):エビデンス不足のため判断保留
- Good practice statement:形式的なエビデンスはないが、臨床上当然と考えられる事項(例:抗菌薬は必ずBPO併用など)
日本は「患者さんの選択肢を残す」姿勢が強く、たとえ保険外やエビデンス不足でも、臨床で行われているものはC1やC2として明記します。
一方、米国は「エビデンスが弱いなら推奨を作らない」スタンス。
日米“ここは同じ”——両者が強調していること


まず大きな共通点からお話ししますね🌸
外用治療の柱はレチノイド+BPO(過酸化ベンゾイル)
日本ではアダパレン(レチノイドの一種)やBPO、それにクリンダマイシン(CLDM)との配合や併用が強く推奨されています。
米国も同じく「レチノイド+BPO」が治療の基本✨
抗菌薬は“単独NG”、BPOなどとセット&長期に使わない
抗菌薬は耐性菌の問題があるので、どちらの国でも「単独では使わないこと」が徹底されています。
日米ともに「BPOなどと併用して、しかも長くは使わないでね!」という方針を明確にしています。
内服抗菌薬の主軸はテトラサイクリン系
日本では炎症が強いニキビに内服抗菌薬を勧めていますが、使う期間はできるだけ短くと強調されています。
米国も同じで、抗菌薬の種類は「ドキシサイクリンを強く推奨」と明言しています。
日米“ここが違う”——重要ポイントを厳選
次に、違いが目立つポイントをご紹介します👀✨
外用選択肢の広さ
日本はアダパレン・BPO・CLDMが中心。長期のCLDM+BPOは耐性が心配なので避けるように書かれていますし、未承認薬や化粧品成分は質の高い臨床試験がないと推奨されません。
一方米国は、レチノイドやBPOに加えてクラコステロン・サリチル酸・アゼライン酸といった成分も「条件付き」で推奨されています✨
ホルモン療法(ピル・スピロノラクトン)
日本はピル・スピロノラクトンについて「推奨しない(C2)」とされています。理由は、保険が効かない、副作用のリスク、試験データの不足など。
一方米国では「条件付きで推奨する」としていて、女性の治療選択肢として取り入れられています💡
イソトレチノイン(内服レチノイド)
日本では未承認薬のためガイドラインでの推奨はありません。
一方アメリカでは「重症」「標準治療で効果がないとき」「瘢痕や心理的負担が大きいとき」に推奨されています。
治療薬の“使い分け” 超まとめ
- 初期~中等症:レチノイド(アダパレン等)+BPOを軸に、炎症が強ければ抗菌薬+BPOなどの配合や内服抗菌薬を短期追加。抗菌薬は必ず併用&短期。
- 維持:レチノイド/BPOで再発抑制。抗菌薬+BPOでの長期維持はしない。
- 重症・瘢痕・心理的負担大:米国はイソトレチノイン推奨。日本は未承認のためガイドライン外。
日米ガイドライン比較表(基本治療・日常ケア)
基本治療・日常ケアについて、日米での違いをまとめました。
※スマホは横向き推奨
| 治療・ケア | 日本ガイドライン | 米国ガイドライン |
|---|---|---|
| 治療の基本方針 | 早期の積極的治療と維持療法で瘢痕予防を重視 | 積極的治療+抗菌薬適正使用(併用・期間短縮)と 維持療法をGood practice |
| 第一選択薬 | 面皰:アダパレン+BPO配合を強く推奨 炎症併存:クリンダマイシン+BPO配合を強く推奨 | 強い推奨:BPO、外用レチノイド、外用抗菌薬、ドキシサイクリン内服。 固定配合薬(レチノイド+BP/抗菌薬+BP)を推奨 |
| 外用抗菌薬 | 面皰には推奨せず(C2) 炎症病変では強く推奨 | 単剤は推奨せず、BPO併用を推奨(耐性対策) |
| 内服抗菌薬 | 強く推奨だが長期は回避。 単剤は回避(BPO等の外用と併用) | 中等症〜重症に使用。使用は可能な限り限定 単剤は 回避(BPO等の外用と併用) |
| イソトレチノイン内服 | 国内では未承認のため ガイドライン推奨記載なし | 強く推奨:重症・瘢痕形成/心理的負担・標準治療不応の場合 |
| ホルモン療法 | 経口避妊薬/LEP:推奨せず(C2) スピロノラクトン:推奨せず(C2) | 条件付き推奨:女性へのCOC、スピロノラクトン |
| スキンケア | 洗顔は1日2回を推奨(C1) | レチノイドは光・刺激に配慮。 日焼け止め併用や保湿で副作用軽減 |
| 化粧・日焼け止め | QOL目的のメイク指導は選択肢(C1) 低刺激・ノンコメドジェニック製品を選択 | レチノイド使用時は日焼け止めを推奨 |
| 食事との関係 | 一律の食事指導は推奨せず(C2) (低GIの報告はあるが見解は一定せず) | 低GI食の効果は相反 乳製品制限の推奨は根拠不十分(明確な推奨なし) |
- BPO:Benzoyl Peroxide(過酸化ベンゾイル)
- COC:低用量混合経口避妊薬
- LEP:低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬
日米ガイドライン比較表(その他の治療)
ここでは、日本では主要でない治療や保健適応外の治療について、日米での違いをまとめています。
※スマホは横向き推奨
| 治療 | 日本ガイドライン | 米国ガイドライン |
|---|---|---|
| 漢方薬 | 荊芥連翹湯=C1 黄連解毒湯・十味敗毒湯・桂枝茯苓丸=C2(保険外) | 個別の漢方推奨はなし. |
| ケミカルピーリング | 面皰/炎症:グリコール酸・サリチル酸マクロゴール =C1(保険外) サリチル酸エタノール=C2 瘢痕:TCA/高濃度グリコール酸=C2 | 全般で推奨を作れない. |
| 光線療法 | 青色光療法(軽中等症)=C2(保険外) PDT(中重症)=C2(保険外) | 推奨を作れない. |
| ステロイド局注 | 炎症性囊腫=B 肥厚性瘢痕=C1 | 大きな丘疹/結節への補助療法として Good practiceで推奨. |
| アゼライン酸外用 | 面皰・炎症性皮疹にC1(保険外) | 条件付き推奨. |
| ビタミン剤(内服/外用) | 内服=C2 外用=C2(保険外) | 推奨を作れない. |
| レーザー治療 | 活動期・瘢痕ともにC2(保険外) | 推奨を作れない. |
- TCA:トリクロロ酢酸
- PDT:Photodynamic Therapy(光線力学療法)
重要ポイント💡 瘢痕(クレーター)の治療について
日本ガイドラインでは、肥厚性瘢痕に対するステロイド局所注射が 「選択肢の一つとして推奨(C1)」となっているのみで、ほかのレーザーや充填剤、ピーリング、外科的処置・凍結は「十分な根拠がないので推奨しない(C2)」とされています。(注:効果がないというわけではありません)
米国ガイドラインは、“瘢痕を作らせないための治療”が中心であり、完成してしまった瘢痕に対する治療の推奨はありません。
したがって、ニキビは放置しないで早めに炎症をおさえる=瘢痕予防がとっても大事なんです。
今あるニキビ、しっかりケアしていきましょうね💪✨
ニキビ治療の新たなアプローチ:腸内環境を整える
日本の最新ガイドラインにはまだ記載がありませんが、プロバイオティクスで腸内環境を整えることが、ニキビ改善への新しいアプローチとして注目され、研究も進んでいます🌸
すでに質の高い研究結果も発表されていて、今後ガイドラインに正式に記載される可能性はある…と私は考えています。ご興味のある方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてくださいね✨
パパ先生からひとこと



こんにちは。夫の消化器内科医、「パパ先生」です。
ガイドラインとは、医師と患者さんが安心して治療を選択できるように示された、非常に重要な指針です。これによって、日本のどの医療機関を受診しても、基本的に同じ水準の医療を受けられるようになっています。
ただし、ガイドラインは“絶対的なルール”ではなく、あくまで「現時点で最も信頼できる医学的根拠に基づいた標準的な治療」を示したものにすぎません。
そのため、実際の診療では、患者さん一人ひとりの症状や合併症、生活背景などを考慮して調整していくことが大切になります。
さいごに
ニキビはどうしても繰り返しやすく、「医者の勧める治療を続けているのに思うように良くならない…」と落ち込んでしまうこともありますよね。そんなときに大切なのは、いま受けている治療が医学的にどの程度根拠のある方法だと理解しておくこと。それだけでも気持ちが少し楽になると思います☺️
また、人によっては保険適用外の自費診療を検討するのも選択肢のひとつです。大事なのは焦らず、一歩ずつ、自分に合ったケアを見つけていくこと。みなさんの参考になれば嬉しいです✨